; )
遺言書の種類と遺言書でできること

この記事では、滋賀・京都で遺言書作成や不動産名義変更のサポートをしている岩渕司法書士事務所が、遺言書の種類と遺言書でできることについて解説します。
私たちが生きていく中で必ず訪れるのが家族や自分が亡くなるということです。
その際に行われるのが「相続」です。
相続を行うときに重要になってくるのが「遺言書」です。
遺言書は各専門家に依頼するだけではなく自分で作成することも可能な書類です。
しかし遺言書には種類があることをご存じですか?
遺言書の種類
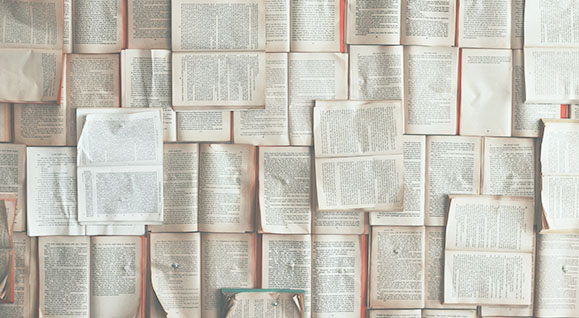
遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
それぞれに異なる特徴があります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは証人2名立会のもとに、遺言者(作成する人)が公証人に口授して行います。
原本が公証役場に保管されるため、紛失・変造などの心配はありません。また、家庭裁判所の検認(遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人は家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。
遺言書は相続人立会のもと、家庭裁判所にて開封されます)などが不要です。
<特徴>
・公証人作成のため不備が少ない
・家庭裁判所の検認が不要
・原本が公証人役場にて保管されるため、紛失などの心配がない(遺言者死亡後、相続人が謄本を請求することができる)
・費用がかかる
自書証書遺言
自書証書遺言とは、全文を自署で作成し、日付・氏名を記入後押印をします。
遺言者本人が作成するため、形式不備で無効にならないよう注意が必要です。
また、開封するためには家庭裁判所の検認が必要となります。
<特徴>
・作成の依頼をしないので費用を抑えられる
・開封時まで内容を第三者に知られる心配がない
・専門家へ相談しない場合、形式不備で無効になってしまう可能性がある
・遺言者自身で保管するため、偽造や紛失などの心配がある
・もし遺言書が発見されない場合は遺言の内容が実現されない
・遺言書を発見した相続人は家庭裁判所にて検認を受けなければ開封することができない
遺言書でできること

遺言書でできることは大きく分けると3つあります。
(1)相続に関すること
(2)財産の処分に関すること
(3)身辺に関すること
これらについて詳しく説明していきます。
(1)相続に関すること
1.相続の割合指定
相続割合は「法定相続」と「遺言相続」があります。遺言書によって、この割合を指定することができます。
2.遺産の分割先の指定
相続人や相続させる物を指定することができます。
3.遺産の分割禁止
相続人が遺産を分割することを最長5年間禁止することができます。
4.遺留分減殺方法の指定
遺留分として受け取る遺産を、侵害された相続人が他の相続人・受遺者に対して遺留分減殺請求を行った場合に、その順序・割合をあらかじめ指定することができます。
5.共同相続人の担保責任の減免・加重
遺産を分割後、相続した財産に欠陥が見つかり損害を受けた相続人は、他の相続人に対して賠償請求をすることができます。その際に、あらかじめこの担保責任の減免・加重を指定しておくと、他の相続人の義務を軽減・加重することができます。
6.遺言執行者の指定
遺言の内容を実現させるための項目で、遺言者が亡くなったあと実際に手続きを行う人をあらかじめ指定することができます。
7.遺贈や生前贈与の持戻しの免除
持戻しとは「遺贈や生前贈与を計算上相続財産に加えること」をいいます。これは相続人間での公平性を図るための制度ですが、遺言書にて持戻しの免除を意思表示することで残った財産のみを計算し相続人間で分配するようにすることができます。
(2)財産の処分に関すること
1.第三者への遺贈
法定では遺産を相続できるのは「血族」と定められています。
これを明記することで、お世話になった友人・内縁の妻・長男の嫁など、相続人以外の第三者に財産の一部またはすべてを贈与することができます。
2.社会に役立てるための寄付
遺産を相続人に相続させるのではなく、公的機関・お寺や教会・各種団体(社会福祉関係や自然保護団体など)へ寄付することができます。
3.信託の設定
信託銀行などに遺産を管理・運営してもらうため、信託先を設定することができます。
(3)身分に関すること
1.認知
内縁の妻など、婚外子を認知することができます。これを行い認知された子は血族となりますので、相続人となることができます。
2.法定相続人の排除・取り消し
法定相続人として決められた相続人を排除、または排除の取消ができます。
3.未成年後見人の指定
遺言者が未成年の親権者であった場合に有効で、自分が亡くなったあと未成年者の親権者がいなくなる場合(ひとり親家庭など)、あらかじめ親権者を設定することができます。
自分に合った遺言書の選択を

どちらの遺言書がいいということはなく、それぞれの事情やケースによって善しあしがあります。
そのため、どちらの方法で遺言書を作成するにしても自分にとって安心できる遺言書を選ぶことが大切です。
また、遺された家族・友人に不毛な争いをさせることを避けるためにも、あなた自身の意思をしっかりと伝えられる遺言書の作成が必要となります。
「自分一人で考えるには難しい」そう感じる人も多いはず。
そんなときはぜひお気軽にご相談ください。
あなたの意思を大切な人に伝えるお手伝いをさせていただきます。
- ブログ筆者:
- 岩渕誠
事務手続きに「愛」をもたらす司法書士。 どんな手続きにもストーリーがあります。それが人生最後のストーリーならなおさらです。この人に事務手続きしてもらって心からよかったと思っていただけるように、愛情込めて事務手続きをいたします。

